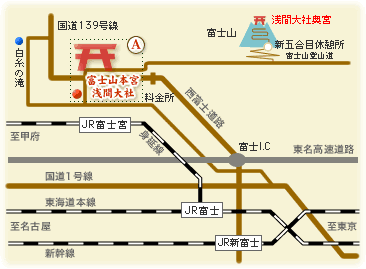静岡県の神社
富士山本宮浅間大社
|
|
|
地図
|
|
東名富士ICより西富士バイパス経由で約20分/新幹線富士駅よりタクシーで約30分/身延線富士宮駅より徒歩約10分 |
| 御祭神 | 浅間大神(あさまのおおかみ) 木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと)※浅間大神の別名 相殿 瓊々杵尊(ににぎのみこと) 相殿 大山祇神(おおやまづみのかみ) |
|---|---|
| 御神徳 | 火難消除・安産・航海・漁業・農業・機械等の守護 |
| 御由緒 | 当大社は、第11代垂仁天皇が、富士山の噴火を鎮めるため、浅間大神を富士山麓に祀られたことに始まります。その後、大同元年(806)に、平城天皇の勅命により、坂上田村麻呂が現在の地に社殿を造営し、浅間大神を山宮より遷し祀られました。以来、全国1300余社に及ぶ浅間神社の総本宮、駿河国一の宮として全国的な崇敬を集める東海最古の名社です。(旧官幣大社) |
| 御祭典 |
例祭(れいさい) 11月3・4・5日古来、4月・9月・11月の申の日に行われた大祭礼のひとつで、様々な稔りに感謝する祭典です。市内では華やかな山車が曳き回され、富士宮囃子(県指定無形民俗文化財)が賑やかに競演される東駿第一の祭りです。初申祭(はつさるさい) 4月初申日縁の深い初申の日に本宮・山宮両社を参拝し、豊かな稔りを祈る祭りです。古くは大祭礼とされ、山宮へ御鉾を渡御する御神幸があるなど、盛大に行われましたが、現在は両社の参拝のみ行われています。流鏑馬祭(やぶさめさい) 5月4・5・6日建久4年(1193)源頼朝が富士の裾野で巻狩を行った際、武運長久・天下太平を祈り奉納したことに始まります。5日本祭日には、神前で古式豊かに祭典が行われた後、鎌倉絵巻さながらに市内を練り歩き、勇壮な流鏑馬が奉納されます。開山奉告祭・閉山奉告祭 7月1日・9月7日7・8月の富士山の山開きにあたり、安全を祈願する祭りです。期間中は富士山頂上に鎮座される奥宮を開き、国家安泰・世界平和を祈念するほか、祈祷・御札、御守りの授与を致しております。御田植祭(おたうえさい) 7月7日当大社の神田のお田植を行うにあたり、富士山よりほとばしる湧水への感謝と五穀豊穣を祈る祭りです。本宮の祭典後、神田の宮で古式ゆかしい御田植神事と早乙女による田植舞が奉納されます。
|