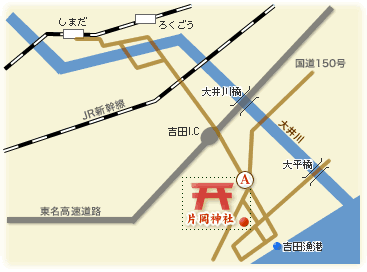| 御祭神 |
底筒男命(そこつつのをのみこと)、中筒男命(なかつつのをのみこと)、表筒男命(うはつつのをのみこと)、息長帯毘売命(おきながたらしひめのみこと)の住吉四柱大神と称奉る神様です。 |
| 御神徳 |
海上安全、国家鎮護、家内安全、産業振興、また和歌学問の神、そして厄除け攘災の神として数々の御神徳を輝かされております。 |
| 御由緒 |
当社は、正保4年に再建された記録がある古社で住吉大明神と称され、明治維新後に片岡神社を正式社名とします。延喜式神名帳の遠江國片岡神社が当社であると伝えます。通称を住吉神社といいます。 現社殿は大正2年に改築。帝室技芸員伊藤平左衛門氏の設計によるものです。 |
| 御祭典 |
歳旦祭 1月1日
年の初めを寿ぎ、併せて今年の神幸祭の日を定め奉ります。年のかわる午前零時には、初詣神酒の振る舞いがあり、大勢の参拝者でにぎわいます。
春祭 4月3日
末社の船玉神社祭が、午前10時からしらす漁・その他の漁船主らによって行われ、稲荷神社祭が午後2時から行われます。合殿の厳島神社、津島神社も併せてお祭りします。
夏越大祓・茅輪神事 6月30日
知らずも身についた罪や災いの元を祓い清め、茅の輪くぐりで家族の健康祈願をします。このときの人形は8月の例祭において海に流されます。
例祭 8月2日
御祭神の一年に一度のお祭りを祝い、皇室の弥栄と国および郷土の隆昌、氏子子孫繁栄を祈ります。8月第1日曜日には神幸祭が行われ、大神輿、奴道中、屋台の舞踊合戦など見どころがいっぱいです。
秋期例祭 10月第2日曜日
古来より当社で「奥の院」と称されている末社の星の宮神社の例祭で、天香香背男命に延命長寿、万民幸福をお祈りします。カラオケ大会などの余興が見どころのお祭りです。

茅輪をくぐる

幼児が曳く大神輿(渡御行列)
|